全国陶磁器産地マップ
日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。




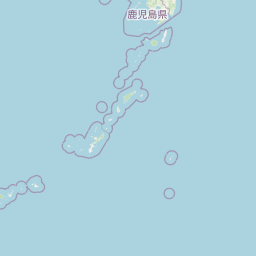
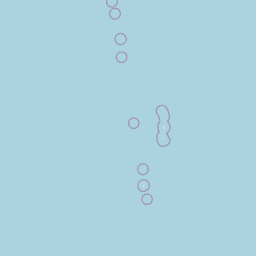



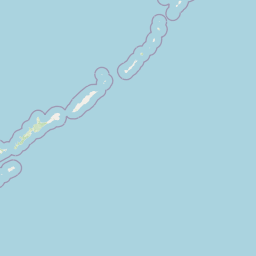





























































































































































| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北の嵐山 | 北海道旭川市旭岡(あさひがおか)一帯 | 北の嵐山(きたのあらしやま)は、工芸・庭園・茶房〜四季折々の里物語が楽しめる場所です。明治時代の開拓当時に行われた煉瓦づくりに起源があり、陶器は雪や氷などをイメージした北国らしい作風が特徴です。また、木製品・染色工房・ガラス工房・ギャラリーや喫茶店が点在し、お洒落で落ち着いた雰囲気が漂っています。住宅地は木が多く、軽井沢町の別荘地や湯布院のような佇まいがあります。 |
| 2 | 北海道 | 小樽焼 | 北海道小樽市 | 小樽焼は、北海道小樽市で約100年ほど生産されていた陶器です。小樽焼は、緑玉織部と呼ばれる釉薬がとろりと掛かった温かみのある陶器で、湯呑やぐい呑、徳利や皿などの生活雑器として親しまれてきました。小樽焼は、明治時代から続いた最後の窯が2007年に閉鎖され、現在は生産されていません。 |
| 3 | 北海道 | こぶ志焼 | 北海道岩見沢市 | こぶ志焼は、1946年に北海道岩見沢で初代「三秋(みあき)」が開窯した陶器です。初窯を焚いたときに桜とともに咲いていた辛夷(こぶし)の木にちなんで「こぶ志窯」と名付けられました。 |
| 4 | 北海道 | 札幌焼 | 札幌市中央区 | 札幌焼は、明治時代末期から大正時代にかけて札幌市で生産されていた陶器です。1899年に蝦夷陶器合資会社が設立され、その後1903年に北海道耐火煉瓦合名会社が設立されました。1914年には札幌陶器製造株式会社が設立され、翌年に中井賢治郎によって買収され、中井陶器工場となりました。この工場は、三国屋南部源蔵商店の後ろ盾を得て、徳利や甕、茶器などを生産していました。しかし、1923年に三国屋が倒産し、後ろ盾を失った中井陶器工場は1924年に中井合名会社に改組されましたが、1925年に操業を停止しました。 |
| 5 | 青森県 | 津軽焼 | 青森県弘前市 | 津軽焼(つがるやき)は、青森県弘前市で焼かれる陶器。 津軽焼の源流は、津軽藩四代藩主信政によって集められた陶工たちが焼いた平清水焼・大沢焼・下川原焼・悪土焼である。現代の津軽焼は、釉薬に黒天目釉やりんご木灰からできる「りんご釉」を使い、素朴な色合いが特徴である。 |
| 6 | 青森県 | 八戸焼 | 青森県八戸市 | 八戸焼(はちのへやき)は、青森県八戸市を中心に生産される焼き物です。江戸時代末期までは庶民の焼き物として知られていましたが、創始年代や創始者などは不明です。 |
| 7 | 岩手県 | 小久慈焼 | 岩手県久慈市 | 小久慈焼は岩手県久慈市で焼かれる陶器で、1813年に相馬の陶工嘉蔵が小久慈天田内の甚六の助けを得て築窯し始まりました。地元の粘土や独自の釉薬を使用し、茶器などを製作しており、茶器などを製作しており、久慈の粘土は鉄分が少ないため、白色がきれいに出る特徴があります。代表的な作品は注ぎ口の長い片口であり、素朴でかわいい風合いが地元で親しまれています。近年はJR東日本の観光列車にも採用されています。 |
| 8 | 岩手県 | 鍛冶丁焼 | 岩手県花巻市 | 鍛冶丁焼は岩手県花巻市で焼かれる陶器。文政年間に、古館伊織が市内の鍛冶町にて窯場を開いたのが始まりである。明治末期になって本家は廃窯し、分家も四代目の戦死によって途絶えた。1947年(昭和22年)に益子で修行した初代阿部勝元が、伝統的な手法を蘇らせて再興した。特色は轆轤による製法、伝統的な登り窯を使った手作りの味にある。そして青緑や乳白色の釉薬は、一見奇抜に見えるが、素朴な落ち着きがある。主に茶碗や酒器、花瓶などの日用雑器を焼いている。 |
| 9 | 岩手県 | 台焼 | 岩手県花巻市 | 台焼は岩手県花巻市で焼かれる陶磁器。花巻温泉郷の一角、台温泉近辺にて焼かれる。「糖青磁釉」と呼ばれる薄緑の色合いが特徴。 |
| 10 | 岩手県 | 藤沢焼 | 岩手県一関市 | 藤沢焼は、1972年に陶芸家の本間伸一さんが岩手県藤沢町(現在の一関市)に窯を築いたことにより始まった焼き物です。 |
| 11 | 宮城県 | 堤焼 | 宮城県仙台市 | 堤焼(つつみやき)は宮城県仙台市で焼かれる陶器。江戸時代中期に仙台藩主、伊達綱村が江戸から今戸焼の陶工・上村万右衛門を招き、日用品を焼かせたのが始まり。堤焼の特徴は、野趣溢れる釉薬にあり、特に黒と白のなまこ釉を同時に掛け流す流し掛けなまこ釉は堤焼独自の特色である。 |
| 12 | 宮城県 | 切込焼 | 宮城県加美郡加美町 | 切込焼(きりごめやき)は、宮城県加美郡加美町の伝統工芸品です。江戸後期から明治の初めにかけて、現在の加美町にあたる宮崎町切込地区を中心に作られました。切込焼の創始ははっきりとわかっておらず、1844~1860年(江戸末期)ごろ全盛であったと伝えられています。 |
| 13 | 宮城県 | 台ヶ森焼 | 宮城県黒川郡大和町吉田台ケ森 | 台ヶ森焼は、宮城県で造られる陶磁器であり、台ヶ森周辺から取れる土を使用して造られています。台ヶ森の周辺の地質は、第四紀に生じた火山活動の影響で凝灰岩などが分布し、銅や鉄を多く含む特徴があります。近隣周辺遺跡からは窯跡や縄文時代の土器が多数出土しており、奈良時代初期には台ノ原・小田原丘陵から多賀城に収める瓦や器を焼く国衛窯が点在していたとされています。1976年に初代窯元 安部勝斎が昇炎式・横炎式・倒炎式の窯を築き、現在の台ヶ森焼が誕生しました。産出される土には、亜炭、鉄、銅など様々な鉱物が含まれ、複雑な色合いが生まれるとされています。 |
| 14 | 秋田県 | 楢岡焼 | 秋田県大仙市南外地域 | 楢岡焼は、秋田県大仙市南外地域にて焼かれる陶器である。独特の群青色の海鼠薬が鮮やかな色合いを出すことで知られている。楢岡焼の創業は、1863年に地元旧家の小松清治が始めたもので、現在は海鼠釉の製品が主体となっている。楢岡焼の工芸技術は、1983年に無形文化財に指定されており、秋田新幹線のE6系のグリーン車の内装にも楢岡焼の青をイメージしたものが使われている。 |
| 15 | 秋田県 | 白岩焼 | 秋田県仙北市角館町白岩 | 白岩焼(しらいわやき)は、秋田県仙北市角館町白岩で焼かれる陶器。秋田県最古の窯元であり、重ね掛けされた褐色の鉄釉と、青みの強い藁灰釉(海鼠釉)の対比に特徴がある。白岩焼は、明治時代から作陶されており、最盛期には6つの窯に5千人の働き手を抱える一大窯業地となりました。現代の白岩焼は昭和時代に復興の機運が高まり、渡邊すなおが和兵衛窯を築窯し、白岩焼の復興に成功しています。 |
| 16 | 山形県 | 平清水焼 | 山形県山形市平清水 | 平清水焼は山形県山形市平清水で焼かれる陶磁器であり、千歳山の原土を用いています。江戸時代に小野藤次平や円仁(慈覚大師)によって教えられたと伝えられています。窯ごとにさまざまな創意工夫が凝らされ、青龍窯の「梨青瓷」「残雪」などが有名です。 |
| 17 | 山形県 | 成島焼 | 山形県米沢市 | 成島焼(なるしまやき)は、山形県米沢市で焼かれる陶器である。米沢藩主の上杉鷹山が家来の相良清左衛門に相馬焼の技法を学ばせて天明元年(1781年)開窯した。絢爛豪華な絵付は用いられず、海鼠釉、黒釉と窯の焼成によって生じる窯変だけで作品を仕上げるのが特徴。成島焼は藩の御用窯として栄え、藩政を支えるほど潤いを見せたが、近代に入り衰微し、大正年間には廃窯した。 |
| 18 | 山形県 | 新庄東山焼 | 山形県新庄市 | 新庄東山焼(しんじょうひがしやまやき)は、山形県新庄市の陶磁器です。天保12年(1841年)に新庄戸沢藩の御用窯として開窯され、170年以上途切れることなく受け継がれてきました。新庄東山焼の特徴は、出羽の雪のかげりと言われる美しい青い色と、全国的に少なくなっている「登窯」で焼かれた陶器の素朴な美しさです |
| 19 | 山形県 | 上の畑焼 | 山形県尾花沢市銀山新畑162-1 | 山形県の陶磁器「上の畑焼」の特徴は、白地に藍色の文様と、中国の風水思想に基づく縁起文様「三多紋」です。三多紋は、桃・柘榴(ざくろ)・仏手柑(ぶっしゅかん)を描いたもので、長寿・魔除け、子孫繁栄、招福を意味します。中国から伊万里焼へ伝わり、そこから上の畑焼へ伝来した吉祥図案で、日本全国で銀山上の畑焼のみが継承しています。 |
| 20 | 山形県 | 深山焼 | 山形県白鷹町 | 深山焼は、山形県白鷹町の伝統工芸です。米沢藩主の上杉鷹山が財政の立て直しのために興した「成島焼」が起源とされています。深山焼は希少製品を焼いた特殊な窯として有名で、江戸時代後期に操業した窯跡があります。昭和40年代に教員であった梅村正芳氏が、この深山焼の復興を目的に陶片研究を開始しました。 |
| 21 | 山形県 | 碁点焼 | 山形県村山市碁点 | 碁点焼(ごてんやき)は、山形県村山市碁点にある陶修窯(とうしゅうがま)で作られている焼物です。深い藍色の化粧土による彩色が特徴で、燻し銀のような黒釉の下地が施されています。薔薇や桜などの花、猫などを描いた作品が多く、女性を中心に愛用されています。 |
| 22 | 福島県 | 大堀相馬焼 | 福島県相馬地方の浪江町大堀地区 | 大堀相馬焼は、福島県を代表する陶器のひとつであり、大堀相馬焼の特徴は、保温性に優れた二重焼、青ひび、駒の絵などの特徴を有しています。略称として大堀焼(おおぼりやき)とも呼ばれています。福島県浪江町大堀地区固有の焼き物から始まり、現在では福島県内の焼き物として認知されています。 |
| 23 | 福島県 | 会津本郷焼 | 福島県大沼郡旧会津本郷町(現在は会津美里町の一部) | 会津本郷焼(あいづほんごうやき)とは、福島県大沼郡旧会津本郷町周辺を産地とする陶器及び陶磁器である。会津本郷せと市が毎年8月第一日曜日に開かれている。会津本郷焼は、江戸時代前期に本郷村で陶土を発見し、水野源左衛門や佐藤伊兵衛によって焼き物の基礎が築かれた。会津本郷焼は厚手で丈夫な仕上がりで知られ、飴釉などの特徴的な釉薬も使われる。この地域は、陶石を原料にした磁器産地として関東以北で唯一のものである。 |
| 24 | 福島県 | 会津慶山焼 | 福島県会津若松市 | 会津慶山焼は、福島県会津若松市で焼かれる陶器である。文禄元年、当時の藩主であった蒲生氏郷が、若松城の前身である黒川城に屋根瓦をふく際に、唐津から陶工を招いて焼かせたのが始まりといわれる。近代に入り、渡部久吉によって、らい鉢、丼鉢、植木鉢、茶器などの日常生活に欠かせない焼き物全般が作られた。平成9年3月31日に福島県から県の伝統的工芸品に指定されている。 |
| 25 | 福島県 | 相馬駒焼 | 福島県相馬地方 | 相馬駒焼(そうまこまやき)とは、福島県相馬地方に産する陶器。相馬焼・駒焼き・田代駒焼ともいう。茶器類が多く、独特のひび焼と走り駒の絵が特徴である。1648年(慶安元年)、京都の仁清のもとで修行した陶芸家、田代源吾右衛門(のちに清治右衛門と改名)が相馬郡中村(現相馬市)に開窯。以後、相馬藩の御用窯として手厚く保護された。窯は福島県指定重要有形民俗文化財田代駒焼登窯として一般公開されているが、現在、相馬駒焼の製作は行われていない。 |
| 26 | 福島県 | 二本松萬古焼 | 福島県二本松市 | 二本松萬古焼(にほんまつばんこやき)は、福島県二本松市で焼かれている陶磁器です。1854年、ふすべ焼の創始者である山下惣介の子「山下春吉」が二本松萬古焼を始めたといわれています。二本松藩主丹羽氏が京都から陶工を呼び寄せ、下級武士に教え産業奨励をしたのが始まりとされています。 |
| 27 | 福島県 | 田島萬古焼 | 福島県南会津郡南会津町関本字下休場728 | 田島万古焼は、福島県の伝統的工芸品で、江戸時代末期に開発されました。田島万古焼は、古来の手びねり万古として指紋を生かして作られています。釉薬を使わずに高温で焼き上げるため、表地には指紋のあとがそのまま残り、深い味わいを出すと同時に、明るい素焼きの色にできあがります。 |
| 28 | 茨城県 | 笠間焼 | 茨城県笠間市 | 笠間焼(かさまやき)は、茨城県笠間市周辺を産地とする陶器である。笠間焼はイノベーションの成功例として高く評価されており、多種多様な焼き物が焼かれている。また、1992年に経済産業省より、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品に指定されている。 |
| 29 | 栃木県 | 益子焼 | 栃木県益子町 | 益子焼は、栃木県益子町で作られている陶器です。益子で採れる土は砂気が多く粘性が少ないため、陶器を作ると割れやすい性質があります。そのため細かい細工が向かず、厚手でぼってりとした見た目のものが多い傾向にあります。 |
| 30 | 栃木県 | 小砂焼 | 栃木県那須郡那珂川町 | 小砂焼(こいさごやき)は栃木県那須郡那珂川町で焼かれる陶器。江戸時代末期、小砂の地で陶土が見つかり、作陶が始まったという。独特の金色を帯びた黄色の金結晶やほんのりとした桃色の辰砂が有名であり、素朴な中にどこか優雅さを感じさせると評される。 |
| 31 | 栃木県 | みかも焼(三毳焼) | 栃木県下都賀郡岩舟町静2147 | みかも焼は、栃木県岩舟町にある窯元「三毳焼小楢窯」でのみ作られている陶器です。栃木県指定の伝統工芸品で、素朴な風合いが特徴です。みかも焼は、三毳山山麓の鉄分が多い土で作られています。鉄分が多い土で焼き上げられており、素朴で温かみのある焼き物です。特に花器類は水が腐りにくく、花が長持ちすると言われています。 |
| 32 | 群馬県 | 渋民焼 | 群馬県渋川市渋川御蔭3775−2 | 群馬県渋川市にある渋民焼の特徴は、焼き物で難しいとされる赤色の陶器を製造することです。渋川市内や伊香保町で採取される土と石を素材に、中国の陶器を参考に赤の釉薬と粉引、灰釉を使用しています。渋民焼は1986年に開窯された比較的新しい窯で、昔ながらの穴窯を使用しています。窯元渋民焼では本格的な陶芸教室も開かれています。 |
| 33 | 群馬県 | 自性寺焼 | 群馬県安中市秋間地域 | 自性寺焼は、群馬県安中市秋間地域で産出する良質陶土で作られる陶器です。金花文の気品に満ちた釉薬を代表として、さまざまなオリジナル釉薬が研究されています。江戸時代中期から明治38年まで安中市下秋間で栄えましたが、最後の窯が益子へ移り、一時途絶えました。1979年に現代の名工青木昇により再興され、群馬県ふるさと伝統工芸品に認定されています。 |
| 34 | 群馬県 | 月夜野焼 | 群馬県利根郡みなかみ町上牧2331 | 月夜野焼は、群馬県利根郡月夜野町で昭和50年1月に開発された陶磁器です。波佐見焼伝来のろくろ技法で成形し、独自に調合した釉薬を施して焼いた特徴ある色合いの焼き物で、燃えるように赤い辰砂釉(しんしゃゆう)が代表的です。伝統の染付技法で描かれた、可憐な草花模様の絵付け作品も数多く取り揃えています。 |
| 35 | 埼玉県 | 飯能焼 | 埼玉県飯能市 | 飯能焼(はんのうやき)とは、かつて埼玉県飯能市で生産されていた陶器である。生産時期は、1832年(天保3年) - 1887年(明治20年)頃とされている。現在一般の店では、明治期まで制作されていた飯能焼の復興を目指して、昭和50年頃から飯能市周辺で再び作成されたものが飯能焼として販売されている。 |
| 36 | 千葉県 | 大多喜焼 | 千葉県大多喜町 | 千葉県の大多喜焼は、地元産の陶土を使って手びねりや蹴ろくろという技法で作られる焼き物です。粗くて独特な質感が特徴で、千葉県指定伝統的工芸品のひとつです。瀬戸・常滑で陶芸の基礎を学んだ陶芸家・井口峰幸さんが、一時途絶えていた大多喜焼を復活させました。房総半島各地を巡って土を集めては試し焼きし、「房州白萩」「房州唐津」などを発表してきました。地元の原料を用いた釉薬(ゆうやく)を使い、その製作に励んでいます。 |
| 37 | 東京都 | 今戸焼 | 東京台東区の今戸や橋場とその周辺(浅草の東北) | 今戸焼は、江戸時代から明治時代にかけて、日用雑器、茶道具、土人形(今戸人形)、火鉢、植木鉢、瓦等を生産していました。天正年間(1573年–1592年)に生産が始まり、幕末期には今戸焼を生産する家が約50軒ほどあったとされています。有名な今戸焼の作例には、「ひょっとこ」や「黒みがきの手あぶり」などがあり、江戸時代には浮世絵に描かれるなど広く知られていました。 |
| 38 | 新潟県 | 無名異焼 | 新潟県佐渡市 | 無名異焼は無名異土(酸化鉄を多量に含んだ赤土)を原料とする焼物である。1819年に、伊藤甚平が佐渡金山の坑内で産する無名異を用いて楽焼を製造したことが始まり。1857年に伊藤富太郎が本焼を始める。技術的には、水簸(水を使った土の精製作業)を行ってからさらに絹目に通すため、他の陶土より粒子が細かく収縮率が大きいのが特徴である。また、成形後は生の内に石や鉄へらなどで磨いて光沢を出し、焼成後には佐渡金山の精錬滓でさらに磨いて、独特の光沢を出す。 |
| 39 | 新潟県 | 庵地焼 | 新潟県阿賀野市保田、通称庵地(あんち)地区 | 庵地焼は、新潟県阿賀野市保田、通称庵地(あんち)地区で焼かれている陶器である。黒色の釉薬が特徴で、「庵地の黒」と呼ばれています。かつては江戸時代から続く“保田焼”(現在の「安田焼」とは異なる)がありましたが、昭和初期に複数の窯があった地区では、第二次世界大戦前後に窯が絶えました。旗野窯はその中で残り続け、様々な食器や雑器を焼いてきました。また、昭和初期には宮之原謙や佐々木象堂などの作家も滞在し、秀作を生み出すなど業界で名声を得ました。近年でも作家が同窯をモデルに小説を発表し、注目を集めています。 |
| 40 | 新潟県 | 村松焼 | 新潟県五泉市 | 村松焼は、天保12年(1841年)から明治25年(1892年)まで新潟県の村松藩の城下町村松で焼かれた陶器である。製品はほとんど陶器であるが、一部半磁器質も作られており、商品の主体は各種の日用品である。製品には鉄釉や灰釉などの釉薬が使われ、伝世品の一部は五泉市村松郷土資料館に残されている。 |
| 41 | 富山県 | 越中瀬戸焼 | 富山県立山町上末、瀬戸地区 | 越中瀬戸焼は富山県立山町上末、瀬戸地区で焼かれる陶器である。地元の「白土」や植物灰などを原料とする釉薬を用いた多彩で大胆な施釉が特徴であり、スティーブ・ジョブズも愛用したとされる。 |
| 42 | 富山県 | 小杉焼 | 富山県射水市小杉地区 | 小杉焼は、1816年(文化13年)頃から1897年(明治30年)頃までの約80年間にわたって焼かれた京焼系相馬焼風の焼き物であり、小杉青磁と呼ばれる緑釉の一種が特徴である。窯跡は黒河二十石字箕輪、戸破、上野、茶屋町の4箇所にあり、現代では陶芸家池上栄一が「小杉焼栄一窯」として制作活動を続けている。小杉焼は、初代高畑与右衛門から4代目までの陶工によって焼かれており、1888年には生産が途絶えたが、昭和期に復興運動が行われ、現代でも制作が続けられている。 |
| 43 | 富山県 | 三助焼 | 富山県砺波市福山326 | 三助焼は、富山県にある地元の土で成形し、草木で作った釉薬を掛けた150年の歴史ある焼き物です。三助焼の特徴は、地場産の土を掘り起こして陶土とし、地元で作られたわらや草木を燃やして作った灰を釉薬として使用することで、全国的にも珍しい淡い緑色の陶器となっていることです。 |
| 44 | 富山県 | 越中丸山焼 | 富山県富山市八尾町丸山 | 越中丸山焼は、富山県を代表する焼き物で、越中瀬戸焼や小杉焼とともに越中近世三大窯に数えられます。素朴な絵付けと洋絵具の愛らしい色合いが特徴です。越中丸山焼の窯跡は、富山平野の南端、飛騨山地へと続く丘陵地帯の中腹にあります。現在は跡地に石碑が建てられています。 |
| 45 | 石川県 | 九谷焼 | 石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市 | 九谷焼(くたにやき)は、石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産される色絵の磁器。五彩手(通称「九谷五彩」)という色鮮やかな上絵付けが特徴である。 |
| 46 | 石川県 | 大樋焼 | 石川県金沢市 | 大樋焼(おおひやき)とは、350年の歴史と伝統をもつ楽焼の脇窯であり、江戸時代初期に加賀藩の前田綱紀が茶道の茶堂として仙叟を招いた際に始まった。大樋焼は石川県金沢市に位置し、手捻り成形や急な焼成など独自の技術で知られる。また、金沢市橋場町には十代大樋長左衛門窯や大樋美術館がある。 |
| 47 | 石川県 | 珠洲焼 | 石川県珠洲市 | 珠洲焼(すずやき)は、12世紀後半頃から15世紀末頃に石川県珠洲市付近で生産された、中世の日本を代表する陶器のひとつ。古墳時代から平安時代にかけて焼かれた須恵器の技法を受け継いでいた。 |
| 48 | 福井県 | 越前焼 | 福井県丹生郡越前町の主に宮崎地区(旧宮崎村)・織田地区(旧織田町) | 越前焼(えちぜんやき)は、福井県丹生郡越前町の主に宮崎地区(旧宮崎村)・織田地区(旧織田町)で焼かれる陶磁器(炻器)。鉄分の多い土を使い、肌色は黒灰色から赤褐色まで変化し、黄緑色の自然釉が流れ落ちる美しさが特徴である。 |
| 49 | 福井県 | 織田焼 | 福井県丹生郡越前町平等 | 織田焼(おたやき)は、福井県丹生郡越前町の織田地区(旧織田町)で焼かれていた陶器です。主に壺や瓶類を産し、古くから織田瓶の名があります。織田焼は、素朴な越前焼とは様相が異なります。大正後期から昭和前期に作られた織田焼の杯には、隣の石川県の九谷焼の影響を受けた鮮やかな絵付けが見られます。 |
| 50 | 福井県 | 氷坂焼 | 福井県越前市氷坂町 | 氷坂焼(ひさかやき)は、福井県丹生郡吉野村氷坂(越前市氷坂町)で明治初年に永宮東助によって創業された焼き物です。昭和40年頃に福井県内で生産される焼き物の名称が「越前焼」に統一されました。氷坂焼は、昭和の時代に北陸トンネルの開通前に今庄駅で売られていた蕎麦の鉢を作っていました。現在では窯跡がわずかに残るのみです。 |
| 51 | 山梨県 | 能穴焼 | 山梨県韮崎市穴山町4281 | 能穴焼(のうけつやき)は、山梨県韮崎市で焼かれている陶器です。窯場の位置が新府城の北にあった能見城の麓、穴山梅雪に緑のある地名「穴山」にあったことから名付けられました。能穴焼は、釉薬への探究から生まれた神秘的な色彩が特徴的です。桃山時代に起源があり、地元の土に拘った歴史ある焼き物です。能穴焼は、代々瓦職人だった初代林茂松が、1935年に山梨にて陶芸に取り組み、「甲斐の陶芸」として再興したもので、能穴焼窯元は山梨県韮崎市にあります。 |
| 52 | 長野県 | 高遠焼 | 長野県上伊那郡高遠町(現伊那市) | 高遠焼は、1812年(文化9年)高遠城に水を引く土管を作るため、美濃から陶芸家を呼んで作陶が始まったとされる。昭和初期に一度は衰退したが、唐木米之助が1975年(昭和50年)に「白山登窯」を構えて、その技術を受け継いだ。赤土を基調として、白と緑など2種類の釉薬を重ねる「二重掛け」が特徴である。 |
| 53 | 長野県 | 松代焼 | 長野県長野市松代地区 | 松代焼は真田氏の城下町として名を馳せ、藩の御用窯として栄えた。寛政の初め頃、唐津で修行を積んだ嘉平次という陶工が開窯し、藍甕を焼いたのが始まり。後の文化13年には松代藩の藩窯として松代焼を奨励した。1972年に復興され現在も製作が続いており、青味を帯びた器肌と豪快に流された青緑色の釉薬が特徴的。松代焼の銅を混ぜた緑色の釉薬は陶土と反応して独特の光沢を生み出すとされる。 |
| 54 | 長野県 | 尾林焼 | 長野県飯田市龍江8132 | 尾林焼は、長野県飯田にある江戸時代後期に飯田藩の藩窯として繁栄した伝統ある焼き物です。長野県下で最も古い尾林古窯は、慶長14年銘のある狛犬によってその年代が判明しています。尾林焼は美濃系の窯と言われており、江戸時代後期嘉永年間に、初代水野儀三郎が飯田藩の御用陶工として瀬戸から飯田に招かれました。その後、土を求めてこの尾林へ築窯して現在の尾林焼が始まりました。 |
| 55 | 長野県 | 天竜峡焼 | 長野県飯田市 | 天竜峡焼は、長野県飯田市の天竜峡で作られている篆刻陶器です。幕末近くに瀬戸の陶工が飯田藩のお庭焼を焼いたことが始まりとされています。明治36年頃から陶器に篆刻を施した茶器や酒器、花器などが作られるようになり、好評を博しました。 |
| 56 | 岐阜県 | 美濃焼 | 岐阜県の東濃地方のうち主に土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市 | 美濃焼(みのやき、Mino-yaki, Mino ware)とは、岐阜県(南部は旧美濃国)の東濃地方のうち主に土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市にまたがる地域で製作される陶磁器の総称である。1978年(昭和53年)7月22日に、通商産業省(現・経済産業省)により伝統的工芸品に指定されている。東濃地方は、日本最大の陶磁器生産拠点であり、中でも土岐市が陶磁器生産量の日本一の街である。 |
| 57 | 岐阜県 | 渋草焼 | 岐阜県高山市 | 渋草焼(しぶくさやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶磁器。平成4年(1992年)3月30日に岐阜県郷土工芸品に指定された。 |
| 58 | 岐阜県 | 小糸焼 | 岐阜県高山市 | 小糸焼(こいとやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶器である。名の由来は高山城下西方の地名小糸坂である。現在の小糸焼は、戦後、長倉三朗によって復活したものである。小糸焼は独特の作風で知られ、特に「伊羅保(イラボ)釉」を発展させた「青伊羅保」という渋く深みのあるコバルトブルーの釉薬が特徴である。1992年(平成4年)3月30日に岐阜県郷土工芸品に指定されている。 |
| 59 | 岐阜県 | 山田焼 | 岐阜県高山市 | 山田焼(やまだやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶器である。 渋草焼、小糸焼と共に現存する焼き物だが、前者が藩主や風流人に好まれたのに対し山田焼は農民、町人のために焼かれた生活雑器である。創始者は稲垣藤四郎といわれる。また、材料の粘土は地元の水田の土を用いていたという。 しかしながら、殖産興業のために山田焼は郡代から推奨されたため、飛騨の焼き物の中で最も長い歴史を持つことになり、現在に至るまで窯の火が絶えたことはない。また明治時代には窯業の技術を応用して土管、煉瓦、瓦などを焼き、大いに繁栄した。 2006年現在は小林陶舎の一軒のみが民芸調の陶器を焼いている。決して飾らない、素朴ながら味わいの深い意匠に人気がある。 1992年(平成4年)3月30日に岐阜県郷土工芸品に指定されている。 |
| 60 | 静岡県 | 志戸呂焼 | 静岡県島田市金谷 | 志戸呂焼は、静岡県島田市金谷(旧金谷町)で焼かれる陶器であり、歴史は室町時代に遡るとされる。志戸呂焼の名前は、西金谷の宿一帯が志戸呂郷と呼ばれたことに由来する。志戸呂焼は大きく3期に分けられ、特徴として褐色または黒釉を使った素朴な釉調があり、鉄分が多くて堅く焼けるため、茶壺に最適とされる。現代でも抹茶や煎茶用の茶器が作られ、名器と呼ばれる壺の裏には「祖母懐」や「姥懐」の刻銘がある。 |
| 61 | 静岡県 | 森山焼 | 静岡県周智郡森町 | 森山焼は、志戸呂焼の流れを汲む陶器で、明治42年に開窯された。加藤藤四郎(民吉)の話に感化された中村秀吉が志戸呂の陶工・鈴木静邨を招き、日用食器、茶器、酒器、花器などを焼いた。大正4年には天皇即位の際に花瓶と置物を献上し、知名度が向上した。現在は、中村陶房、静邨陶房、晴山陶房、田米陶房の4軒の窯元があり、個性的な意匠が見られる。特に静邨陶房(鈴木龍)の真っ赤な釉薬を使った赤焼や、晴山陶房(松井晴山)の虎布釉が特に知られている。 |
| 62 | 静岡県 | 賤機焼 | 静岡県静岡市 | 賤機焼は、江戸初期に太田太郎衛門によって開陶され、徳川家康より徳川家の御用窯として繁栄した陶器。赤土に鉄分を多く含むために素地が赤茶色であり、辰砂や釉裏紅といった技術を用いて鮮やかな色彩を出すことが特徴である。また、釉薬を一切使わず、焼き締めによる窯変を意匠とした南蛮手も独自の技術であり、表面がゴツゴツしていて、肌合いはかなり荒い。 |
| 63 | 愛知県 | 瀬戸焼 | 愛知県瀬戸市とその周辺 | 瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市とその周辺で生産される陶磁器の総称。日本六古窯の一つ(瀬戸窯)。東日本で広く流通し、瀬戸物は陶磁器を指す一般名詞化した。瀬戸焼は、越前焼(福井県越前町)、丹波立杭焼(兵庫県丹波篠山市)、備前焼(岡山県備前市)、常滑焼(愛知県常滑市)、信楽焼(滋賀県甲賀市)とともに、日本六古窯として日本遺産に認定された。 |
| 64 | 愛知県 | 赤津焼 | 愛知県瀬戸市赤津町94-4 | 赤津焼(あかづやき)は、瀬戸焼のうち、愛知県瀬戸市街地の東方にある赤津地区で焼かれる焼物。赤津焼は、瀬戸窯とともに発展した窯で平安時代の開窯とされ、当地には室町時代の窯跡である小長曽陶器窯跡が残る。戦国時代、瀬戸では「瀬戸山離散」と呼称される窯屋の急激な減少が発生し、多くの窯が美濃地方に移った。赤津焼は国の伝統的工芸品にも指定されており、現在は赤津焼会館にて赤津地区の焼物を展示・販売している。 |
| 65 | 愛知県 | 常滑焼 | 愛知県常滑市を中心とし、その周辺を含む知多半島 | 常滑焼(とこなめやき)は、愛知県常滑市を中心とし、その周辺を含む知多半島内で焼かれる炻器。日本六古窯の一つ。 2017年(平成29年)4月29日、常滑焼は、瀬戸焼(愛知県瀬戸市)、越前焼(福井県越前町)、丹波立杭焼(兵庫県丹波篠山市)、備前焼(岡山県備前市)、信楽焼(滋賀県甲賀市)、とともに、日本六古窯として日本遺産に認定された。 |
| 66 | 愛知県 | 御深井焼 | 名古屋城内の御深井丸 | 御深井焼(おふけいやき)とは、主として17世紀後半から18世紀にかけて盛行した灰釉に長石を加えて透明度を高めた釉を施すとともに摺絵や型打ちや貼付文などを用いた陶器類の呼称である。 |
| 67 | 愛知県 | 犬山焼 | 愛知県犬山市今井 | 江戸元禄年間、今井村(現在の犬山市今井)において、郷士奥村伝三郎が今井窯を築き、焼物を作ったのが始まりです。その後、犬山城主成瀬正寿が文化7年(1810年)丸山に開窯、文政年間(19世紀)には、犬山藩お庭焼として発展し現在に至ります。 作風は、中国明時代の呉州赤絵を手本とする呉州風赤絵・犬山城主成瀬正寿の意匠による光琳風の桜と紅葉を描いた雲錦手が特徴で、素朴で優雅な陶器として愛用されています。 |
| 68 | 愛知県 | 川名焼 | 愛知県名古屋市昭和区川名山町 | 川名焼は、愛知県名古屋市昭和区川名山町で焼かれた陶磁器です。川名山焼とも呼ばれます。川名焼は、1848~1854年頃に瀬戸の陶工で川本治兵衛の門弟加藤新七が開窯しました。製品は染付磁器でしたが、瀬戸の窯屋からの抗議により、当時最新の絵付技術であった、銅版転写による絵付け製品のみ生産することとなりました。 |
| 69 | 愛知県 | 豊楽焼 | 愛知県名古屋市中区大須 | 豊楽焼(ほうらくやき)は、愛知県名古屋市中区大須(旧・前津)で焼かれた軟質陶器です。江戸時代後期から大正年間にかけて、130年以上にわたって焼かれました。現在は途絶えています。 |
| 70 | 三重県 | 四日市萬古焼 | 三重県四日市市 | 萬古焼(ばんこやき、万古焼)は、陶磁器・焼き物の一つで、葉長石(ペタライト)を使用して耐熱性に優れた特徴を持つ。陶器と磁器の間の性質を持つ半磁器(炻器)に分類される。三重県四日市市を中心に、土鍋などが生産されている。市内の橋北地区と海蔵地区で盛んに造られ、四日市市指定無形文化財となっている。また、萬古焼は1959年頃、主原料の粘土にペタライトを混ぜることで熱膨張しにくい土鍋を開発してシェアを伸ばし、1970年代には国産土鍋の大半を占めるようになった。1979年には経済産業大臣によって伝統的工芸品に指定されました。 |
| 71 | 三重県 | 伊賀焼 | 三重県伊賀市 | 伊賀焼は、三重県伊賀市にて焼かれている陶器。伊賀焼に使われる古琵琶湖地層の土は細かな気孔が多く、熱を蓄えることに優れている。中世に生産された蹲(うずくまる)でも知られる。伊賀焼の郷・伊賀市には、2021年時点に約50軒の窯元があり、伊賀市の槙山に近い五位ノ木窯跡などで中世の時代には豊富な陶土と薪の燃料を利用し、信楽焼に似た擂鉢や甕、壺などが焼かれた。 |
| 72 | 三重県 | 阿漕焼 | 三重県津市 | 阿漕焼は三重県津市で焼かれる陶器で、名の由来は地名の阿漕浦に因み、萬古焼の流れを汲んでおり、200年余りの歴史がある。三重県指定伝統工芸品として知られている。特徴としては、器自体は萬古焼の流れを汲みながら、九谷焼のような絵付けを施すことが挙げられ、朱や緑、黄色、紫、紺青などの色彩を巧みに用いる点が特徴的である。 |
| 73 | 三重県 | 御浜焼 | 三重県南牟婁郡御浜町 | 御浜焼は、三重県の南部にあった焼き物です。紀伊半島の南半分は険しい山々がそびえており、陶土に恵まれていないことから、御浜焼は現在は生産されていません。 |
| 74 | 滋賀県 | 信楽焼 | 滋賀県甲賀市信楽 | 信楽焼(しがらきやき)は、滋賀県甲賀市信楽を中心に作られる陶器で、日本六古窯のひとつに数えられる。一般には狸の置物が著名であるが、後述のように多様な発展を遂げている。信楽の土は、耐火性に富み、可塑性とともに腰が強いといわれ、「大物づくり」に適し、かつ「小物づくり」においても細工しやすい粘性であり、多種多様のバラエティーに富んだ信楽焼が開発されている。 |
| 75 | 滋賀県 | 湖南焼 | 滋賀県大津市長等山下、札之辻、または園城寺下鹿関町地域 | 湖南焼(こなんやき)は1851年(嘉永4年)-1854年(嘉永7年)の間に、滋賀県大津市長等山下、札之辻、または園城寺下鹿関町地域で作られた陶磁器である。落款印には「永樂」、「河濱支流」、「三井御濱」の押捺を持ち、永樂保全が最後に築いた窯として近世陶磁史に名を残す。 |
| 76 | 滋賀県 | 膳所焼 | 滋賀県大津市 | 膳所焼(ぜぜやき)とは、滋賀県大津市にて焼かれる陶器。茶陶として名高く、遠州七窯の一つに数えられる。黒味を帯びた鉄釉が特色で、素朴でありながら繊細な意匠は遠州が掲げた「きれいさび」の精神が息づいている。 |
| 77 | 滋賀県 | 下田焼 | 滋賀県湖南市東寺2丁目11-9 | 滋賀県湖南市で生産される「近江下田焼」は、滋賀県知事指定の伝統的工芸品です。江戸時代中期(1750年頃)、下田地域(現:湖南市)の村人が陶芸に適した土を発見したことが始まりと言われています。明治以降の機械化による大量生産に押され、最盛期には12軒以上あった窯元も徐々に廃窯が相次ぎ、一度途絶えてしまいました。1989年に廃窯となったが、1994年に最後の後継者である小迫一氏によって再興されました。 |
| 78 | 滋賀県 | 八田焼 | 滋賀県甲賀市 | 八田焼は、滋賀県甲賀市で作られている地域ブランドです。江戸時代の1655年(明暦元年)に、信楽から陶工を招いて作られ始めました。農家の副業として盛んになり、徳利・片口・神器・茶器などが焼かれてきました。 |
| 79 | 滋賀県 | 湖東焼 | 彦根藩本領(現・滋賀県彦根市域) | 湖東焼'(ことうやき)は、江戸時代後期に日本の彦根藩で始まった陶芸および、それによって生産される陶磁器である。湖東とは、彦根藩が所在した琵琶湖東岸を指す広域地名である。 青磁、赤絵や赤絵金彩、色絵などで絵付けした磁器が多く、大坂を経由して江戸など全国へ販売された。1829年(文政12年)に彦根藩本領(現・滋賀県彦根市域)で生産され始め、1842年(天保13年)に藩営化された。藩主井伊掃部頭家の許で発展したが、奨励・保護した井伊直弼が幕府大老在任中に暗殺されると職人が離散して一気に衰退し、明治時代に途絶した。その後、1986年(昭和61年)に復興事業が立ち上げられている。 |
| 80 | 京都府 | 京焼 | 京都府 | 京焼は、日本の陶磁器のうち、京都で焼かれる作品の総称です。色絵桜楓文木瓜形鉢や色絵飛鳳文隅切膳などが代表的な作品として挙げられます。京焼は経済産業大臣指定伝統的工芸品としての名称は京焼・清水焼として知られており、窯の所在地は東山を中心に洛東や洛北にも点在しています。歴史的には清水焼の他、粟田口焼、音羽焼、八坂焼、御菩薩池焼、修学院焼、清閑寺焼、御室焼などが含まれています。京焼は一度焼成した後に上絵付けを施す技法を用いた陶器が多く、作家ごとの個性が強いのが特徴です。また、江戸時代には京焼の陶工が他の陶磁器産地に招かれて作風や技術を全国に広める役割を果たしました。 |
| 81 | 京都府 | 清水焼 | 京都府五条通の大和大路通から東大路通(東山通)に至る区間の北側 | 清水焼は、清水寺への参道である五条坂界隈に多くの窯元があったことから、京都府で焼かれる陶磁器の代表とされる。若宮八幡宮社の境内には「清水焼発祥の地」との石碑が建ち、毎年8月8日から10日には清水焼で装飾された神輿が出る「陶器祭」が行われる。京都府では、経済産業大臣指定伝統的工芸品として「京焼・清水焼」が認定されている。 |
| 82 | 京都府 | 楽焼 | 京都府 | 楽焼は、日本の伝統的な陶器の一種で、樂吉左衛門家における焼物です。手捏ねと呼ばれる方法で成形され、750℃から1,200℃で焼成された軟質施釉陶器です。楽家では、茶道具や炭道具として使用されます。楽焼は、楽家初代長次郎が千利休の指導を受けて生み出した茶碗「楽茶碗」が始まりであり、黒楽や赤楽などの特徴的な製法があります。楽家の楽焼を本窯、傍流の楽焼を脇窯と呼びます。 |
| 83 | 京都府 | 朝日焼 | 京都府宇治市 | 朝日焼(あさひやき)は京都府宇治市で焼かれる陶器。宇治茶の栽培が盛んになるにつれ、茶の湯向けの陶器が焼かれるようになった。江戸時代には遠州七窯の一つにも数えられている。朝日焼は原料の粘土に鉄分を含むため、焼成すると独特の赤い斑点が現れるのが最大の特徴である。 |
| 84 | 大阪府 | 吉向焼 | 大阪府交野市私市8丁目25−6 | 吉向焼は、江戸時代後期に愛媛県出身の戸田治兵衛が大阪で開窯した陶器です。当初は亀次にちなんで亀甲焼と呼ばれていましたが、大阪城代の水野忠邦から「吉向」の号を拝領し、現在の吉向焼と名乗るようになりました。 |
| 85 | 大阪府 | 古曽部焼 | 摂津国嶋上郡古曾部村(現大阪府高槻市古曽部町) | 古曾部窯で生産された陶器。近年、五十嵐家五代の当主たちによる明治末期までの古曾部焼と、大正年間、「窯元も含む(古曾部)村の有志」が京都五条坂の陶工河合磊三を招き、河合の成型した器を古曾部窯にて焼成した磊三古曾部(らいぞうこそべ)(復興古曾部)とに区分されている。 |
| 86 | 兵庫県 | 丹波立杭焼 | 兵庫県丹波篠山市今田地区付近 | 丹波立杭焼は、兵庫県丹波篠山市今田地区付近で焼かれる陶器。主に生活雑器を焼いてきた。丹波焼、または立杭焼ともいう。起源は平安時代にまで遡るといわれ、六古窯の一つに数えられる。中世の丹波焼の特徴は赤っぽい土肌にかかる、焼き締めによる自然釉に特徴がある。備前焼、信楽焼に比べ、若緑色のおとなしめで爽やかな作品が多い。江戸時代以後は釉薬や技法が多様になったが、現代の丹波焼でもその風合いを引き継いだ民芸調の作品が多く見られる。 |
| 87 | 兵庫県 | 出石焼 | 兵庫県豊岡市出石町 | 出石焼(いずしやき)は、兵庫県豊岡市出石町一帯で焼かれる磁器。出石白磁ともいう。出石焼は国内でも珍しい白磁を中心とした焼き物であり、透き通るように白い磁肌に、浮き彫りや透かし彫りによる精緻な紋様が際立っています。出石藩では、江戸時代中期に大量の白磁の鉱脈が発見され、1801年に藩窯が開設され、本格的な生産が始まりました。出石焼は明治9年に品質改良に成功し、名声を高めており、1980年には経済産業大臣によって伝統的工芸品に指定されました。 |
| 88 | 兵庫県 | 明石焼 | 兵庫県明石市 | 明石焼(あかしやき)は、明石市の郷土料理であり、玉子焼の別称です。 |
| 89 | 兵庫県 | 赤穂雲火焼 | 兵庫県 | 赤穂雲火焼は、大嶋黄谷の雲火焼を復元し、兵庫県伝統的工芸品に指定されている陶器。1848年から1849年にかけて大嶋黄谷が赤穂逗留中の今戸焼の陶工・作根弁次郎から陶技を習得し、1852年に雲火焼の焼成に成功した。雲火焼の特徴は、白地に橙色、黒色の夕焼け空にも似た美しい窯変が現れる点である。黄谷は第1回内国勧業博覧会に作品を出品して花紋褒賞を受賞し、20世紀に入ると桃井香子と長棟州彦が雲火焼を復元し、1993年には兵庫県伝統的工芸品に指定された。 |
| 90 | 兵庫県 | 王地山焼 | 兵庫県丹波篠山市河原町431 | 王地山焼は、兵庫県丹波篠山市河原町の王地山で焼かれる兵庫県指定の伝統的工芸品です。透明感のある緑がかった青色と半立体の模様が特徴で、中国風の青磁、染付、赤絵を主とした磁器窯として名声を博しました。王地山焼は、江戸時代末期の1818年に当時の篠山藩主である青山忠裕が、京焼の陶工・欽古堂亀祐を招いて始めた藩窯が発祥と言われています。嘉永年間(1848~54年)には、気品に富んだ上手作を焼いていますが、廃藩と共に明治2年(1869年)に廃窯となりました。 |
| 91 | 兵庫県 | 八鹿焼 | 兵庫県養父市八鹿町 | 八鹿焼(ようかやき)は、明治時代から大正時代にかけて兵庫県養父市八鹿町で焼かれた土焼の陶器です。島根県の石州瓦の職人が八鹿で瓦を焼いたことから始まり、瓦や水甕、擂鉢、火鉢などの生活に必要な陶器を生産しました。高級品を焼く出石焼に対して、八鹿焼は日常生活に使う陶器を作りました。八鹿焼は昭和4年(1929年)に窯を閉じたことから、今では幻となった養父市の特産品です。 |
| 92 | 兵庫県 | 珉平焼 | 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野 | 珉平焼(みんぺいやき)は、兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野で賀集珉平が文政年間(1818-1830)に創業した陶器です。別名伊賀野焼・淡路焼とも呼ばれます。京焼陶工の尾形周平より陶技を学び、淡路島の白土を用いて黄南京・緑釉・柿釉などの作品を試作しました。また、尾形周平を淡路に招き、京焼のデザインや釉薬調合の技術を作品に取り入れました。珉平焼は黄・緑・赤色が特徴的で、色鮮やかなものが多くあります。 |
| 93 | 奈良県 | 赤膚焼 | 奈良県奈良市、大和郡山市 | 赤膚焼(あかはだやき)は奈良県奈良市、大和郡山市に窯場が点在する陶器である。赤みのある乳白色の柔らかな素地と奈良絵文様を特色とする。 |
| 94 | 和歌山県 | 瑞芝焼 | 和歌山県和歌山市 | 瑞芝焼は和歌山県和歌山市で焼かれる陶器である。鈴丸焼・滅法谷(めっぽうたに)焼ともよばれる。「瑞(みずみずしい)芝」という銘が表すとおり、透明感のある青緑色が特色。中国龍泉窯の流れを汲む。寛政8年(1796年)に岡崎屋阪上重次郎が紀州藩の官許を受けて和歌山市畑屋敷新道町(旧鈴丸町)藻屑川のほとりで開窯、享和元年(1801年)滅法谷に窯を移して滅法谷焼とも呼ばれた。享和元年(1801年)には紀州徳川家十代藩主徳川治寶に芝の緑色を表現した青磁を焼くように命じられ、京都の名工、青木目米(あおきもくべえ)の指導を受けながら大成した。 |
| 95 | 鳥取県 | 因久山焼 | 鳥取県八頭郡八頭町 | 因久山焼は、明和年間(1764年~72年)に鳥取藩主池田侯によって京都から招聘された六兵衛が開窯し、尾崎家初代治良右衛門と芹沢家二代亀五郎に陶技を伝授したことに始まる。1795年(寛政7年)には御国産として保護を受け、享和・文化(1801年~18年)頃には、信楽の陶工勘蔵が新たな陶法をもたらし、息子勘助とともに名品を残すなど、現在知られる因久山焼の基礎が確立した。因久山焼は茶陶が多く、藁灰釉、緑釉、白釉、黒釉などを単調に流しかけた例が多い。捻り物にも優品は知られるが、細やかな細工の作品は少なく、江戸時代から続く七室の連房式登窯を焼き継ぐ芹澤家が窯元として知られる。 |
| 96 | 鳥取県 | 牛ノ戸焼 | 鳥取市河原町 | 牛ノ戸焼は鳥取県鳥取市河原町にて焼かれる陶器。天保年間に因幡の陶工、金河藤七によって開窯され、その後は小林梅五郎に継承された。作品は実用性において評価を得ており、「用の美」を追求したものである。トレードマークの梅紋は初代から継承されている刻印である。擂り鉢や椅子などの日用雑器のほかに、釉薬の緑と黒を半々に振り分けた特徴的な作品もある。他にはイッチン描き(筒描き)も見られる。民藝運動家たちの影響が強い焼き物であり、芸術性と実用性を兼ね備えている。 |
| 97 | 鳥取県 | 浦富焼 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富3174-3 | 浦富焼(うらどめやき)は、鳥取県岩美郡で江戸時代末期に焼かれた陶磁器です。浦富海岸の山中より陶石を運び、乳母ヶ懐の山裾に窯を築いて焼かれました。1971年3月、桐山城跡の浦富側山麓に登り窯が築かれ、江戸時代に用いられた同じ陶石を生地として、白磁・染付・黒刷毛を主に現代生活に即した日用品、工芸品が制作されています。 |
| 98 | 鳥取県 | 上神焼 | 鳥取県倉吉市 | 上神焼(かずわやき)は、鳥取県の郷土工芸品です。江戸時代中期の宝暦年間(1751年〜1764年)に開窯され、1941年に中森音吉が京都から来住して再興されました。上神焼は、地元の土や鳥取県の特産である梨の木の灰、初代から続く赤い釉薬、辰砂(しんしゃ)を使用して作られています。三代目は、辰砂釉などの伝統を受け継ぎながら、新しい手法で作品を創作しています。 |
| 99 | 鳥取県 | 法勝寺焼 | 鳥取県西伯郡南部町落合257番地 | 法勝寺焼は、鳥取県南部町にある窯元です。明治36年(1903年)に初代安藤秀太郎が築窯し、約250年前に江州(滋賀県)の陶工丈助により製陶が始められた伝統を受け継いでいます。法勝寺焼の特徴は、伝統を大切にしながらも新しい現代感覚を持ち、日常使いできることです。土瓶などに良く表れている焼き上がりの柔らかみが特徴で、簡潔にして気品高く、茶人・雅客の方に愛蔵されています。 |
| 100 | 島根県 | 石見焼 | 島根県江津市 | 石見焼は島根県江津市を中心に旧石見国一帯で焼かれる陶器で、飯銅(はんどう)と呼ばれる大甕で知られる。石見焼の甕は耐水性に優れ、貯水に最適であり、全国から需要があった。現在は傘立てやマグカップなども製作されており、1994年に国の伝統的工芸品に指定されている。 |
| 101 | 島根県 | 布志名焼 | 島根県松江市玉湯町 | 布志名焼は、江戸時代中期に舩木与次兵衛村政によって開窯され、松江藩の藩命で土屋善四郎の指導のもと品質が向上しました。布志名特有の黄釉色絵物は国内外に販路を広げ、明治頃に全盛を迎えました。さらに、明治時代には民芸運動の影響を受け、化粧泥で模様を施したスリップウェアと呼ばれる技法が取り入れられました。 |
| 102 | 島根県 | 出西焼 | 島根県斐川町(現・出雲市)出西 | 出西窯は島根県斐川町(現・出雲市)出西にある窯元であり、戦後、農村出身の次男三男であった5人の若者たちが共同体的な窯元として始めました。柳宗悦や河井寛次郎、舩木道忠、濱田庄司、バーナード・リーチたち「民藝運動家」の影響を受け発展し、現在でも共同体的な窯元運営を続け、現代の「民藝」の旗手的存在となっています。 |
| 103 | 島根県 | 袖師焼 | 島根県松江市幸町803−13 | 袖師焼(そでしやき)は、島根県松江市で製造されている陶器の地域ブランドです。出雲に伝わる技法をベースに、地元産の土と釉薬にこだわり、丈夫でシンプルな中にも潤いを持つのが特徴です。明治10年(1877年)に初代・尾野友市が松江市上乃木の皇子坂に開窯したことが始まりです。二代目・岩次郎氏は、明治26年に窯を宍道湖岸の袖師浦に移しました。 |
| 104 | 島根県 | 母里焼 | 島根県安来市 | 母里焼(もりやき)は、島根県安来市で作られている陶器の地域ブランドです。江戸時代後期の1844年に、松江藩の支藩である母里藩の産業・文化事業として始まったとされています。くすんだ青色が特徴で、かつては地区のどの家にもあったと言われています。母里焼は、石見焼の伝統技法である「しの作り」によって作られています。石見焼は、18世紀の中頃から島根県西部(石見地方)で焼かれ始めた陶器の総称で、耐酸・耐塩・耐水に優れています。漬物甕など貯蔵用容器として全国的に有名で、現在では料理にあう皿やカップなど日用に使う陶器も豊富にあります。 |
| 105 | 島根県 | 楽山焼 | 愛媛県松山市 | 楽山焼(らくざんやき)は、島根県松江市西川津楽山で焼かれる焼物です。出雲焼の一種で、萩焼の陶工である倉崎権兵衛が延宝年間(1673~1681)に茶陶を焼き始めました。楽山焼の特徴は、伊羅保釉で淡い山吹色に仕上げた「伊羅保写し」や「刷毛目」の技法を用いたものが多く見られることです。また、御用窯としての格式と品位を重んじる楽山焼では、土灰づくりとその調合に関しての工夫が施されています。 |
| 106 | 島根県 | 錦山焼 | 島根県安来市黒井田町西十神町1987 | 錦山焼(きんざんやき)は、島根県安来市の毘売塚(ひめづか)の山麓にある窯場で作られている陶磁器です。錦山焼の特徴は、独特な成型と多種多彩な釉薬の色調、その配色にあります。鉄釉や白色釉を用いていた時期もありましたが、現在は辰砂釉、呉須釉と青磁釉・飴釉などの調合・発色に励んだ5代目の中島武男の技術を継承しています。 |
| 107 | 島根県 | 八幡焼 | 島根県安来市広瀬町 | 八幡焼(はちまんやき)は、島根県安来市広瀬町に窯元を構える陶磁器です。呉須釉と呼ばれる藍色の顔料が特徴で、淡く上品な青釉薬の緑が象徴的です。八幡焼は、1723年に萩から招いた陶工によって開窯されたと言われています。江戸時代には松江藩の支藩であった広瀬藩の直属の窯となり、廃藩置県により民営の窯となりました。 |
| 108 | 島根県 | 萬祥山焼 | 島根県出雲市大津町2669 | 萬祥山焼(ばんしょうざんやき)は、島根県の出雲市で作られている陶器です。明治5年(1872年)頃、日野家八代源左衛門が地元の粘土を使用して焼いたのが始まりで、当初は来原焼と呼ばれていました。後に大津の森広操軒の命名で「萬祥山焼」と呼ばれるようになりました。萬祥山焼は、茶道具類が主体で、酒器や花器などがあります。伊羅保釉・青銅釉が特徴です。 |
| 109 | 島根県 | 御代焼 | 島根県雲南市 | 御代焼(みじろやき)は、島根県雲南市で作られている陶器の地域ブランドです。江戸時代、2代松江藩主・松平綱隆によって良質な土と認められた雲南市加茂町三代の土で作られています。御代焼は、1842年に布志名の職人五助が開いた御代窯で作られています。流行に左右されない日用の美を追求した茶碗、花瓶、皿、水盤などの日用陶器を作っています。 |
| 110 | 島根県 | 温泉津焼 | 島根県大田市温泉津町 | 温泉津焼(ゆのつやき)は、島根県大田市温泉津町で焼かれる陶磁器。歴史は宝永年間(18世紀初)頃に始まり、主に「半斗(水瓶)」を造り、日本各地に出荷していた。第二次世界大戦後にはプラスチックなどの化学製品が発達し需要が低迷したが、現在は窯が再興されている。特徴としては、耐用年数の長い日用的な食器に適し、耐火性の高い石見粘土を使用し、1300度以上の高温で焼成され、硬く割れにくいとされている。 |
| 111 | 島根県 | 江津焼 | 島根県江津市 | 石見焼(いわみやき)は、島根県江津市を中心とした石見地方で焼かれている陶器の総称です。18世紀の中頃から作られており、平成6年には国の伝統的工芸品に指定されています。石見焼の特徴は、吸水性が低く強固で、塩分や酸・アルカリに強い素地です。陶土が良質であるため高温の焼成が可能で、堅牢で、耐酸、耐アルカリ性が高いのも特徴です。 |
| 112 | 岡山県 | 備前焼 | 岡山県備前市周辺 | 備前焼は、岡山県備前市周辺を産地とする陶磁器であり、日本六古窯の一つに数えられる。産地である備前市伊部地区で盛んであり「伊部焼(いんべやき)」とも呼ばれる。特徴として、釉薬を使わず「酸化焔焼成」によって赤みの強い味わいや窯変によって生まれる模様が挙げられる。茶器、酒器、皿などが多く生産され、使い込むほど味が出ると言われる。また、窯変の種類には胡麻、桟切り、緋襷、牡丹餅、青備前、黒備前、白備前などがある。 |
| 113 | 岡山県 | 虫明焼 | 岡山県瀬戸内市(旧邑久町)虫明 | 虫明焼(むしあけやき)は、岡山県瀬戸内市(旧邑久町)虫明にて焼かれている陶器。虫明焼の始まりは諸説あるが、およそ300年ほど前とされる。虫明焼は、岡山藩筆頭家老の伊木家のお庭焼として生まれたとされるが、伝世品から判断してやや疑わしい。虫明焼は、天然松灰を主原料に自家精製した透明の灰釉を用い、その色調は施釉の濃淡や松木の焚き方によって灰釉のおとなしい青色、赤色、黄色などに変化する。造りは薄作りで淡性な粟田風のひなびた風情がある。 |
| 114 | 岡山県 | 酒津焼 | 岡山県倉敷市 | 酒津焼(さかづやき)は、岡山県倉敷市で1869年(明治2年)から続く焼物です。倉敷最古の焼物で、明治初期に築かれた窯で焼成されています。酒津焼は、酒津の良質の土を用いて登り窯で焼き上げられます。肉厚で堅牢などっしりとした質感と、飾りをできるだけ抑えたシンプルなデザインが特徴です。釉薬をしっかりかけて厚手に仕上げた重厚な作りと、光沢ある素朴な風合いが特長です。壊れにくさと使いやすさを持ち合わせており、日常での使用に最適です。 |
| 115 | 岡山県 | 羽島焼 | 岡山県倉敷市郊外 | 羽島焼は、岡山県倉敷市郊外で焼かれる陶磁器。日用品を意識して製作されたものが多く、無駄な飾りや技巧を省いた質素な作柄で知られる。 |
| 116 | 広島県 | 宮島焼 | 広島県廿日市市宮島口地区 | 宮島焼(みやじまやき)とは、広島県廿日市市宮島口地区で焼かれる陶器。宮島口は対岸に宮島を望み、その厳島神社参拝の際の縁起物として焼かれた。別名を神砂焼(しんしゃやき)、御砂焼(おすなやき)とも呼び、宮島の砂を粘土に混ぜて焼いている。 |
| 117 | 広島県 | 姫谷焼 | 広島県福山市加茂町百谷 | 姫谷焼(ひめたにやき/ひめややき)は、備後国広瀬村姫谷(現・広島県福山市加茂町百谷)で江戸時代(17世紀)に制作されていた色絵陶磁器。当時の備後福山藩主であった水野勝種の指示によって生産が始められたといわれている。肥前有田(伊万里焼)、加賀(九谷焼)とともに17世紀の日本国内で磁器の生産に成功した三つの産地の一つであった。ごく短期間操業した後に廃絶したため、現在では幻の焼き物とされている。 |
| 118 | 山口県 | 萩焼 | 山口県萩市 | 萩焼(はぎやき)とは山口県萩市一帯で焼かれる陶器。一部長門市・山口市にも窯元がある。長門市で焼かれる萩焼は、特に深川萩(ふかわはぎ)と呼ばれる。古くから「一楽二萩三唐津」と謳われるほど、茶人好みの器を焼いてきたことで知られる焼き物である。萩焼の特徴は原料に用いられる陶土とそれに混ぜる釉薬の具合によって生じる「貫入」と使い込むことによって生じる「七化け」がある。貫入とは器の表面の釉薬がひび割れたような状態になることで、七化けとはその貫入が原因で、長年使い込むとそこにお茶やお酒が浸透し、器表面の色が適当に変化し、枯れた味わいを見せることである。素地の色を生かすため、模様は地味だが根強いファンが多く、市内界隈には新規を含め、多数の窯元が存在する。 |
| 119 | 山口県 | 堀越焼 | 山口県防府市江泊235-3 | 堀越焼は昔ながらのひもづくりを製法とし、陶土をひも状に巻いて、それを叩いて締めて大きな甕(かめ)や壷をつくっていた。 周辺の農村で使う実用的な粗陶器をつくる窯場だった。 そこで昔ながらの伝統を続ける唯一の窯元が賀谷初一(かやはついち)さんという方であった。 |
| 120 | 山口県 | 末田焼 | 山口県防府市江泊118-40 | 末田地区と呼ばれる地域にあり、この地域で作られる焼き物は「末田焼」と呼ばれています。 明治時代後期に土管の製造で栄え、その後食器の製造やたこ壺づくりへと形を変えましたが、職人の高齢化や後継者問題などで数多くあった窯元は廃業してしまいました。2017/10/31 |
| 121 | 山口県 | 星里焼 | 山口県下関市小月町 | 星里焼(せいりやき)は、山口県豊浦郡小月村(下関市小月町)で江戸時代末期に清末藩の御用窯として開窯した焼物です。小月村には星の里という古称があり、同年頃の当主を藤崎星里と呼んだため、別称星里焼の名があります。星里焼は亜鉛結晶を製出し、結晶釉を施した焼物です。 |
| 122 | 徳島県 | 大谷焼 | 徳島県鳴門市大麻町大谷 | 大谷焼は、徳島県鳴門市大麻町大谷で作られる炻器である。大谷焼の陶祖は豊後国(大分県)の文右衛門で1780年(安永9年)頃に始まり、寝轆轤と呼ばれる独特の轆轤で制作される大甕で知られる。大谷焼は元々染付磁器が焼かれていましたが、後に藍染の需要に応じた大甕を焼くようになりました。現在は壺、皿、徳利、片口、茶器などの小物も焼かれています。2003年に経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されています。また、大谷焼はアニメ作品とのコラボ作品も制作され話題となっています。 |
| 123 | 香川県 | 理平焼 | 香川県高松市 | 理平焼(りへいやき)は香川県高松市で焼かれる陶器。高松焼ともいう。初代高松藩主、松平頼重が京都の陶工、森島作兵衛を招き焼かせた御庭焼がルーツとなっている。作兵衛が高松に在住した際に理兵衛と改名したため、理兵衛焼と呼ばれるようになった。現在、理平焼と呼ばれるのは明治に入ってからで、栗林公園の北門前へ窯場を移転してからである。窯創設以来、一度も廃窯することなく、脈々と受け継がれ、現在は14代目である。理平焼の特徴は土の性質によって生じる、藤色の器肌にある。また、京焼の流れを汲む蒔絵の技法を用いた作品も試みられている。 |
| 124 | 香川県 | 神懸焼 | 香川県小豆郡小豆島町 | 神懸焼(かんかけやき)は、香川県小豆郡小豆島町で作られている焼物です。楽焼の手法による焼物で、1875年(明治8年)に寒霞渓の土産品として作られました。神懸焼は、明治の初頃に平賀源内を源とする陶工・祖春が、神懸山(寒霞渓)の麓に陶窯を築いて始めました。その後、加賀の国久谷より陶工・香悦が来島し、神懸焼を受け継ぎました。香悦は独自の流れ釉薬を完成させ、優美さ、堅牢さを有する独自の焼物を作り上げました。 |
| 125 | 香川県 | 岡本焼 | 香川県三豊市財田町財田上7239ー13 | 岡本焼は、香川県三豊市豊中町の岡本地区で採れる土を使った陶器です。素朴な色合いが特徴で、土釜や鍋、豆炒り瓦などの生活雑器の生産が中心でした。製品は俗にほうろくといわれています。岡本焼は、1986年に香川県の伝統的工芸品に指定されました。明治末期から昭和初期にかけて最盛期を迎えましたが、その後生活習慣の変化などで需要が減少し、現在は1人しか職人が残っていません。 |
| 126 | 愛媛県 | 砥部焼 | 愛媛県砥部町 | 砥部焼は、愛媛県砥部町を中心に作られる陶磁器である。一般には、食器、花器等が多い。愛媛県指定無形文化財。後背の山地から良質の陶石が産出されていたことから、大洲藩の庇護のもと、発展を遂げた。やや厚手の白磁に、呉須と呼ばれる薄い藍色の手書きの図案が特徴。他窯の磁器と比較して頑丈で重量感があり、ひびや欠けが入りにくいため道具としての評価が高い。砥部焼の多くは手作り成形のため、全国的に見ても決して大産地や有名産地ではないが、独特の風合いが愛好家に評価されている。讃岐うどんの器としても砥部焼はよく用いられる。 映画『瀬戸内海賊物語』(砥部町出身の大森研一が監督)においては、重要なシーンのアイテムとして砥部焼が用いられた。 |
| 127 | 愛媛県 | 水月焼 | 愛媛県松山市 | 水月焼は、1903年に好川恒方が松山の自宅に築窯し始めた窯作品を指します。好川恒方は、鹿野派の画家である父のもとに生まれ幼少のころから絵をたしなんで育ちました。築窯してからは動植物や山水などをモチーフとした作品を得意としました。 |
| 128 | 愛媛県 | 楽山焼 | 愛媛県松山市 | 楽山焼(らくざんやき)は、愛媛県松山市で焼かれる陶器です。1678年に陶工の倉崎権兵衛が、二代目松山藩主松平綱隆の命により窯場を開いたのが始まりとされています。楽山焼の最大の特徴は蟹の紋様で、激流に棲む蟹の勇壮さが引き立つデザインとなっています。三代目藩主である松平定長が「あな寒し かくれ家いそげ 霜の蟹」という句に感銘を受けてから蟹の紋様を入れるようになったと言われています。 |
| 129 | 高知県 | 内原野焼 | 高知県安芸市 | 内原野焼は高知県安芸市で焼かれる陶器で、1829年(文政12年)頃に内原野に初めて窯が開かれ、徳利、すり鉢などの日用品を中心に焼かれました。特徴として、木灰やワラ灰を原料にした釉薬を使った温かみのある素朴な風合いがあります。昭和初期まで大型の焼き物を作っていましたが、生活様式の変化に伴い需要が減少しました。窯元の衰退を受け、1965年(昭和40年)から1969年(昭和44年)にかけて内原野焼の復興と発展を目指して取り組みが行われました。2020年時点で、野村窯、福留窯、原峰窯、陽和工房の4つの窯元が存在しています。 |
| 130 | 高知県 | 尾戸焼 | 高知県高知市小津町 | 尾戸焼(おどやき)は、江戸時代に土佐国尾戸で産出した陶器で、承応2年(1653年)に山内忠義の命で開窯された。初期は藩窯と御庭焼を折衷した性格であり、享保12年(1727年)に初期の窯場が焼失し、元文4年(1739年)に新たな窯場が再建されて陶器が生産された。現在は「土居窯」・「谷製陶所」が継承している。 |
| 131 | 高知県 | 能茶山焼 | 高知県高知市小津町 | 能茶山焼(のうさやまやき)は、高知県高知市で作られている陶磁器です。1820年(文政3年)に土佐藩が砥部や有田の職人を招いて開窯し、明治維新後は民窯として存続しました。能茶山独特の絵付けと「能茶山製」「茶山」「茶」「サ」などの銘が入れられていることです。製品は、皿鉢や徳利、花入、茶碗や皿などの雑器類など多種にわたります。 |
| 132 | 福岡県 | 小石原焼 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 小石原焼(こいしわらやき)は、福岡県朝倉郡東峰村にて焼かれる陶器。主に生活雑器が焼かれる。江戸時代前期の1662年(寛文2年)に、福岡藩3代藩主・黒田光之が肥前国伊万里から陶工を招いて窯場を開いたのが始まりである。柳宗悦によって提唱された民藝運動の中で小鹿田焼が脚光を浴びた後、そのルーツである小石原も注目されるようになり、1954年(昭和29年)、柳やバーナード・リーチらが小石原を訪れ、「用の美の極致である」と絶賛したことで全国的に知られるようになった。 |
| 133 | 福岡県 | 上野焼 | 福岡県田川郡香春町、福智町、大任町 | 上野焼は、豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の引き上げの際、加藤清正が連れ帰った尊楷(上野喜蔵)が、細川忠興の小倉城入城の際に招かれ、豊前国上野に開窯したのが始まりである。上野焼の特徴は他の陶器と比べると生地が薄く、軽量であり、釉薬も多種多様で窯変を生み出し、絵付けは基本的に用いないとされている。 |
| 134 | 福岡県 | 高取焼 | 福岡県朝倉郡東峰村、福岡市早良区高取 | 高取焼は、福岡県朝倉郡東峰村、福岡市早良区高取などで継承されている陶器で、400年ほどの歴史を持つ県下有数の古窯です。高取焼は元々、福岡県直方市にある鷹取山の麓にて焼かれており、朝鮮出兵の際に黒田長政が陶工、八山(日本名・八蔵重貞)を連れ帰って焼かせたのが始まりとされています。江戸時代には黒田藩の御用窯として繁栄し、遠州七窯の一つにも数えられ、茶陶産地として名を高めました。高取焼は技術や作風が時代によって変化し、それぞれ特徴的な釉薬が使われています。現在も数カ所の窯元が残存し、伝統を受け継いでいます。 |
| 135 | 福岡県 | 蒲池焼 | 福岡県柳川市及び瀬高町 | 蒲池焼(かまちやき)は福岡県柳川市及び瀬高町で焼かれる焼き物。「幻の土器」と称される。色は黒、赤、白の3つであり、「雲華」や「繧繝」と呼ばれる黒や白の斑紋があるものもあり、色の違いは焼き方や土によって変わる。生の状態の時に椿の葉で磨いた後、松の木で焚いた900度の窯で焼くことで重厚な色合いの土器ができる |
| 136 | 福岡県 | 一の瀬焼 | 福岡県うきは市浮羽町朝田一の瀬地区 | 一の瀬焼は福岡県うきは市浮羽町朝田一の瀬地区を中心に焼かれる陶磁器を指し、朝田焼(あさだやき)とも呼ばれる民窯である。1600年頃から始まる歴史は大きく5期に分かれており、現在6ヵ所の窯元が存在している。また、これらの窯元は1950年頃に有志によって立ち上げられた「一の瀬陶器株式会社」が独立・分家したものであり、伝説の「祥瑞」との関わりも示唆されている。各窯元は、伝統的な作風を残しながらも差別化を図り、様々な作品を取り扱っている。 |
| 137 | 福岡県 | 星野焼 | 福岡県八女市星野村 | 星野焼は、福岡県八女市にある星野村の土で作られる陶器です。江戸時代に久留米藩の御用窯として栄え、葉茶壷や茶道具などの名品を生み出しました。明治中期に一度途絶えましたが、昭和44年に山本源太氏が再興し、現在では星野を代表する美術工芸として高く評価されています。 |
| 138 | 福岡県 | 二川焼 | 福岡県みやま市高田町 | 二川窯(ふたがわかま)は、筑後国(現、福岡県)三池郡二川で焼かれた陶磁器。江戸時代末期頃、弓野焼の陶工米作によって始められた。二川焼では弓野焼に似た松絵の甕などが引き継がれたが、第二次世界大戦の終戦近くで廃絶した。弓野焼の職人が指導していることから、弓野焼との差が小さく判別は困難だが、松絵の描き方や白化粧土の掛け方が弓野焼ほど精緻ではなく、用いる胎土にも違いが見られる。 |
| 139 | 佐賀県 | 有田焼 | 佐賀県有田町 | 有田焼は、天草陶石や泉山陶石などを原料として佐賀県有田町を中心に焼かれる磁器であり、「伊万里(いまり)」や伊万里焼とも呼ばれています。この磁器は初期伊万里、古九谷様式、柿右衛門様式、金襴手などの様式に大別され、1977年に経済産業大臣指定伝統工芸品に指定されています。有田は日本国内で長期にわたって磁器の生産を続けており、有田内山は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 |
| 140 | 佐賀県 | 伊万里焼 | 佐賀県有田町 | 伊万里焼(いまりやき)は、有田(佐賀県有田町)を中心とする肥前国(現代の佐賀県および長崎県)で生産された磁器の総称。製品の主な積み出し港が伊万里であったことから、消費地では「伊万里焼」と呼ばれた。有田の製品のほか、三川内焼、波佐見焼、鍋島焼なども含む。[ |
| 141 | 佐賀県 | 唐津焼 | 佐賀県唐津市 | 唐津(からつやき)は、近世初期以来、現在の佐賀県東部・長崎県北部造された陶器の総称。作風・技法も多岐にわたる。茶碗は古くから「一楽二萩三唐津」と称されて名高い。分派の武雄古唐津焼と共に、日本の伝統的工芸品に指定されている。 |
| 142 | 佐賀県 | 白石焼 | 佐賀県三養基郡みやき町北茂安 | 白石焼は佐賀県三養基郡みやき町で焼かれる伝統的な陶器で、元々は磁器が中心でした。有田や唐津と並び、肥前の代表的な磁器産地として知られ、"東目の皿山"とも呼ばれています。宝暦年間に枡谷金右衛門によって始められ、隣国の久留米藩などで評判を得ました。寛政12年には藤崎百十が天草の陶石を使い磁器を焼き始め、1806年には佐賀鍋島藩の分家である白石鍋島家の御用窯として、伊万里大川内から陶工を招き本格的な磁器産地としました。白石焼は民芸調の作品が主流で、伝統技法に現代的な絵付けを加えた作品が特徴で、白を基調とした端整な気品と懐かしさを感じさせる独特の風合いがあります。 |
| 143 | 佐賀県 | 肥前吉田焼 | 佐賀県嬉野市 | 肥前吉田焼は古くから生活向けの食器類を焼いてきており、確立されたスタイルは存在しない。主に染付磁器・色絵などを焼いているが、窯元によって伝統的な青磁から現代的なデザイン、伝承や物語をあしらった意匠のものなど様々である。また作品も湯呑み、茶碗、酒器からコーヒーカップ、花瓶まで幅広い。非常にリベラルな作風を持った陶磁器といえる。 |
| 144 | 佐賀県 | 肥前尾崎焼 | 佐賀県神埼市 | 肥前尾崎焼は佐賀県神埼市で焼かれている陶器である。九州でも有数の古窯で、伝承によると弘安の役(1281年)後、半ば捕虜とした尾崎で暮らした敗残兵が、大陸から持ち込んだ技術で製陶を始めたという。ルーツについては他にも諸説あるが、地元で「蒙古屋敷の跡」と伝わる場所があり、古いの陶器が出土する。安土桃山時代には長右衛門右京という陶工が作った茶器を豊臣秀吉に献上したところ、大変激賞し右京に御朱印を賜ったと伝えられる。江戸時代には幕府への献上品にもなった。江戸末期には生活雑器を焼いており、規模は小さいながらもそれなりに繁栄した。 |
| 145 | 佐賀県 | 武雄古唐津焼(黒牟田焼/多々良焼/小田志焼) | 佐賀県武雄市山内町 | 武雄古唐津焼は、1992年に開窯した康雲窯が代表的な窯元です。康雲窯では、唐津系の製法で主に茶碗、皿、湯飲みなどの器を作陶しています。窯主の山口康雄氏の作品は、唐津焼の影響が色濃く、赤絵をあしらった華やかさも特徴です。 |
| 146 | 佐賀県 | 志田焼 | 佐賀県嬉野市塩田町大字久間 久間乙3073 | 志田焼は、佐賀県有田の東17kmにある肥前磁器産地の窯場で焼かれた陶磁器です。18世紀半ば頃から天草陶石による磁器の焼成が開始され、全盛期は文化年間以降でした。 |
| 147 | 長崎県 | 三川内焼 | 長崎県佐世保市の三川内 | 三川内焼(みかわちやき)は、平戸焼(ひらどやき)ともいう、長崎県佐世保市の三川内で生産される陶磁器である。昭和53年(1978年)に経済産業大臣指定伝統的工芸品の認証を受けている。針尾島の網代陶石と肥後天草陶石を用いた白磁に藍色で絵付けがされた物に代表され、デンマークの博物館長を務めたエミール・ハンノーバーは、著書『日本陶磁器考』の中で「1750年から1830年の間の日本磁器の中では白色に光り輝く最高の製品」と称賛している。 |
| 148 | 長崎県 | 波佐見焼 | 長崎県東彼杵郡波佐見町付近 | 波佐見焼は、21世紀になって新たに誕生した「やきもの」の産地であり、北欧デザインやJapandiなモダンな食器が注目されています。食器類は「波佐見焼」として地域団体商標に登録されています。波佐見町でのやきものの歴史は古く、江戸時代の後期には染付磁器の生産量では日本一でした。近年、地域が一丸となり、「現代生活に合った大衆向けでリーズナブルな日用食器」としての方向性を打ち出しています。 |
| 149 | 長崎県 | 現川焼 | 長崎県 | 現川焼(うつつがわやき)は長崎県にて焼かれた陶器。1691年(元禄4年)から1748年(寛延元年)頃までの約60年間焼き継がれた。 現川焼陶窯跡には、1704年(宝永元年)に建てられた窯観音があり、現川焼の創始者である田中宗悦・同甚内・重富茂兵衛等にかかわる銘が刻まれている。 |
| 150 | 熊本県 | 小代焼(小岱焼) | 熊本県荒尾市、南関町、熊本市など県北部 | 小代焼は熊本県北部で焼かれる陶器で、寛永9年(1632年)に始まりました。釉薬の深い色合いと伝統技法による躍動感あふれる文様が特徴です。明治維新後は衰退しましたが、昭和に復興し、2003年に経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されました。窯は小岱山麓に多く築かれています。 |
| 151 | 熊本県 | 天草陶磁器(内田皿山焼/水の平焼/高浜焼/丸尾焼) | 熊本県天草地方 | 天草陶磁器は熊本県天草地方で焼かれる陶磁器類の総称で、国の伝統的工芸品に指定された際に、新たに名付けられることになった呼び名である。内田皿山焼、高浜焼、水の平焼、丸尾焼の四つが主な産地であり、良質の陶石が採れたことから焼き物作りが盛んになった。 |
| 152 | 熊本県 | 高田焼(八代焼) | 熊本県八代市 | 高田焼(こうだやき)は熊本県八代市で焼かれる陶器で、八代焼(やつしろやき)ともいう。焼き物には珍しい象嵌を施すところが特徴。初期は上野焼の手法を用いていたが、後に高田焼の特色でもある白土象嵌の技法を完成させた。現在もこの流れを汲む技法を堅持しつつも、新たな彩色象嵌を開発するなどして発展を遂げている。 |
| 153 | 大分県 | 小鹿田焼 | 大分県日田市の山あいに位置する小鹿田皿山地区(日田市源栄町皿山) | 小鹿田焼は、江戸時代中期の1705年(宝永2年)若しくは1737年(元文2年)に、江戸幕府直轄領(天領)であった日田の代官により領内の生活雑器の需要を賄うために興されたもので、山を隔てた現在の小石原(現在の福岡県)から招かれた陶工の柳瀬三右衛門と、彼を招いた日田郡大鶴村の黒木十兵衛によって始められた。朝鮮系登り窯を用い、飛び鉋(カンナ)、刷毛目、櫛描きなどの道具を用いて刻まれた幾何学的紋様を特徴とする。掘り出した後に10日乾燥させて木槌で砕き、「唐臼」で搗いて土粒に水を加え、何度も濾して泥にし、2カ月かけて仕上げる。陶土は黄褐色の粘土で、鉄分が多いため釉薬との相乗効果で美しく仕上がる。 |
| 154 | 宮崎県 | 都城焼 | 宮崎県都城市吉之元町5105−17 | 宮崎県都城市には、霧島の麓にある小さな窯元「都城焼 太郎窯」があります。日用雑器を中心に作陶しており、土の温かみや素朴さ、釉の彩りを求めています。 |
| 155 | 宮崎県 | 小松原焼 | 宮崎県宮崎市 | 小松原焼(こまつばらやき)は、宮崎県宮崎市で生産される焼物です。表面に細かな割れを生じさせる「鮫肌」の技法などが特徴で、力強く重厚なため、花器・つぼ類から日常生活用品に至るまで、さまざまな用途に利用されています。 |
| 156 | 鹿児島県 | 薩摩焼 | 鹿児島県内 | 薩摩焼は、鹿児島県内で焼かれる陶磁器であり、竪野系、龍門司系、苗代川系があります。主な窯場は姶良市の龍門司窯、日置市(旧東市来町)の苗代川窯、鹿児島市の長太郎窯などが挙げられます。薩摩焼は、「白もん」と呼ばれる豪華絢爛な色絵錦手の陶器と、「黒もん」と呼ばれる大衆向けの雑器に分かれています。豊臣秀吉の文禄・慶長の役の際に来日した朝鮮人が島津義弘の保護の下で発展した初期の薩摩焼は、2002年に国の伝統的工芸品に指定されました。 |
| 157 | 鹿児島県 | 種子島焼 | 鹿児島県種子島 | 種子島焼は、17~18世紀頃から始まったと言われる陶器です。鉄分を多く含む種子島の土を使い、登り窯で焼き締めた素朴で味わい深い焼き物です。日用雑器を中心として作られていましたが、明治35年まで住吉能野で焼かれました。 |
| 158 | 沖縄県 | 壺屋焼 | 沖縄県那覇市壺屋地区及び読谷村 | 壺屋焼(つぼややき)は沖縄県那覇市壺屋地区及び読谷村その他で焼かれる沖縄を代表する陶器の名称。登り窯を中心に灯油窯やガス窯なども用いながら伝統の技術と技法を受け継いでいる。 |
| 159 | 沖縄県 | 琉球焼 | 沖縄県 | 琉球焼とは、陶芸用語で琉球(沖縄)の焼き物のことを指します。17世紀初頭に薩摩から朝鮮人陶工が招かれ、製陶技術を学んだと言われています。 |
