全国陶磁器産地マップ
日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。














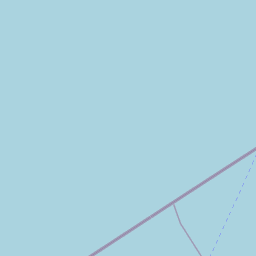











| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 美濃焼 | 岐阜県の東濃地方のうち主に土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市 | 美濃焼(みのやき、Mino-yaki, Mino ware)とは、岐阜県(南部は旧美濃国)の東濃地方のうち主に土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市にまたがる地域で製作される陶磁器の総称である。1978年(昭和53年)7月22日に、通商産業省(現・経済産業省)により伝統的工芸品に指定されている。東濃地方は、日本最大の陶磁器生産拠点であり、中でも土岐市が陶磁器生産量の日本一の街である。 |
| 2 | 岐阜県 | 渋草焼 | 岐阜県高山市 | 渋草焼(しぶくさやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶磁器。平成4年(1992年)3月30日に岐阜県郷土工芸品に指定された。 |
| 3 | 岐阜県 | 小糸焼 | 岐阜県高山市 | 小糸焼(こいとやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶器である。名の由来は高山城下西方の地名小糸坂である。現在の小糸焼は、戦後、長倉三朗によって復活したものである。小糸焼は独特の作風で知られ、特に「伊羅保(イラボ)釉」を発展させた「青伊羅保」という渋く深みのあるコバルトブルーの釉薬が特徴である。1992年(平成4年)3月30日に岐阜県郷土工芸品に指定されている。 |
| 4 | 岐阜県 | 山田焼 | 岐阜県高山市 | 山田焼(やまだやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶器である。 渋草焼、小糸焼と共に現存する焼き物だが、前者が藩主や風流人に好まれたのに対し山田焼は農民、町人のために焼かれた生活雑器である。創始者は稲垣藤四郎といわれる。また、材料の粘土は地元の水田の土を用いていたという。 しかしながら、殖産興業のために山田焼は郡代から推奨されたため、飛騨の焼き物の中で最も長い歴史を持つことになり、現在に至るまで窯の火が絶えたことはない。また明治時代には窯業の技術を応用して土管、煉瓦、瓦などを焼き、大いに繁栄した。 2006年現在は小林陶舎の一軒のみが民芸調の陶器を焼いている。決して飾らない、素朴ながら味わいの深い意匠に人気がある。 1992年(平成4年)3月30日に岐阜県郷土工芸品に指定されている。 |
