全国陶磁器産地マップ
日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。










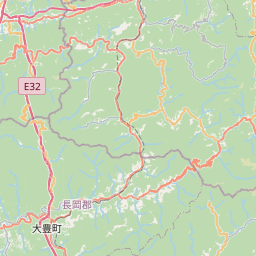





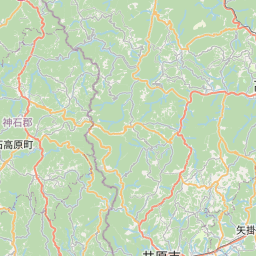

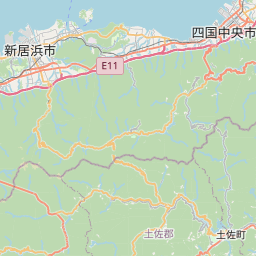
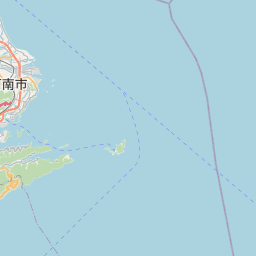

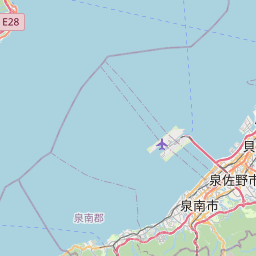




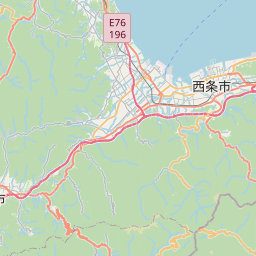








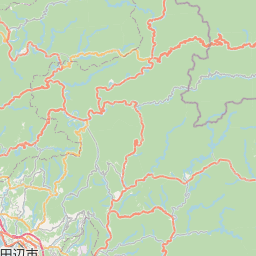



| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 理平焼 | 香川県高松市 | 理平焼(りへいやき)は香川県高松市で焼かれる陶器。高松焼ともいう。初代高松藩主、松平頼重が京都の陶工、森島作兵衛を招き焼かせた御庭焼がルーツとなっている。作兵衛が高松に在住した際に理兵衛と改名したため、理兵衛焼と呼ばれるようになった。現在、理平焼と呼ばれるのは明治に入ってからで、栗林公園の北門前へ窯場を移転してからである。窯創設以来、一度も廃窯することなく、脈々と受け継がれ、現在は14代目である。理平焼の特徴は土の性質によって生じる、藤色の器肌にある。また、京焼の流れを汲む蒔絵の技法を用いた作品も試みられている。 |
| 2 | 香川県 | 神懸焼 | 香川県小豆郡小豆島町 | 神懸焼(かんかけやき)は、香川県小豆郡小豆島町で作られている焼物です。楽焼の手法による焼物で、1875年(明治8年)に寒霞渓の土産品として作られました。神懸焼は、明治の初頃に平賀源内を源とする陶工・祖春が、神懸山(寒霞渓)の麓に陶窯を築いて始めました。その後、加賀の国久谷より陶工・香悦が来島し、神懸焼を受け継ぎました。香悦は独自の流れ釉薬を完成させ、優美さ、堅牢さを有する独自の焼物を作り上げました。 |
| 3 | 香川県 | 岡本焼 | 香川県三豊市財田町財田上7239ー13 | 岡本焼は、香川県三豊市豊中町の岡本地区で採れる土を使った陶器です。素朴な色合いが特徴で、土釜や鍋、豆炒り瓦などの生活雑器の生産が中心でした。製品は俗にほうろくといわれています。岡本焼は、1986年に香川県の伝統的工芸品に指定されました。明治末期から昭和初期にかけて最盛期を迎えましたが、その後生活習慣の変化などで需要が減少し、現在は1人しか職人が残っていません。 |
