全国陶磁器産地マップ
日本の陶磁器産地を一目で把握できるリストを作成しました!この一覧は、全国各地の伝統ある焼き物産地を都道府県順に整理しています。情報源としては、日本の陶磁器産地一覧を参照しております。このリストを通して、日本の豊かな陶磁器文化の多様性とその地域ごとの特色をご紹介できればと思います。
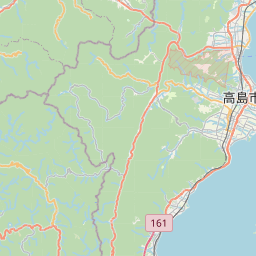

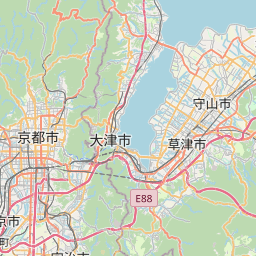



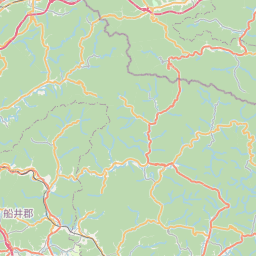




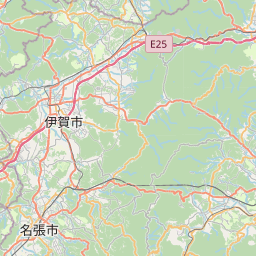




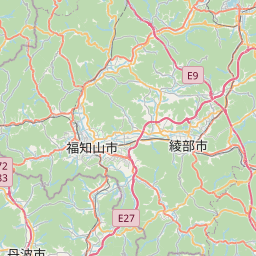
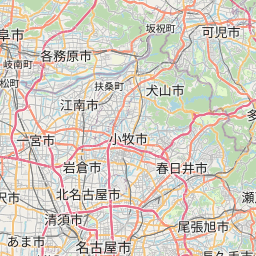









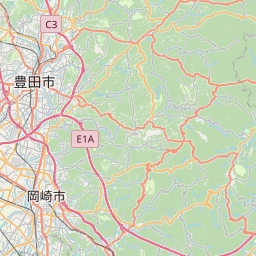










| # | 都道府県 | 陶磁器名称 | 場所 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 信楽焼 | 滋賀県甲賀市信楽 | 信楽焼(しがらきやき)は、滋賀県甲賀市信楽を中心に作られる陶器で、日本六古窯のひとつに数えられる。一般には狸の置物が著名であるが、後述のように多様な発展を遂げている。信楽の土は、耐火性に富み、可塑性とともに腰が強いといわれ、「大物づくり」に適し、かつ「小物づくり」においても細工しやすい粘性であり、多種多様のバラエティーに富んだ信楽焼が開発されている。 |
| 2 | 滋賀県 | 湖南焼 | 滋賀県大津市長等山下、札之辻、または園城寺下鹿関町地域 | 湖南焼(こなんやき)は1851年(嘉永4年)-1854年(嘉永7年)の間に、滋賀県大津市長等山下、札之辻、または園城寺下鹿関町地域で作られた陶磁器である。落款印には「永樂」、「河濱支流」、「三井御濱」の押捺を持ち、永樂保全が最後に築いた窯として近世陶磁史に名を残す。 |
| 3 | 滋賀県 | 膳所焼 | 滋賀県大津市 | 膳所焼(ぜぜやき)とは、滋賀県大津市にて焼かれる陶器。茶陶として名高く、遠州七窯の一つに数えられる。黒味を帯びた鉄釉が特色で、素朴でありながら繊細な意匠は遠州が掲げた「きれいさび」の精神が息づいている。 |
| 4 | 滋賀県 | 下田焼 | 滋賀県湖南市東寺2丁目11-9 | 滋賀県湖南市で生産される「近江下田焼」は、滋賀県知事指定の伝統的工芸品です。江戸時代中期(1750年頃)、下田地域(現:湖南市)の村人が陶芸に適した土を発見したことが始まりと言われています。明治以降の機械化による大量生産に押され、最盛期には12軒以上あった窯元も徐々に廃窯が相次ぎ、一度途絶えてしまいました。1989年に廃窯となったが、1994年に最後の後継者である小迫一氏によって再興されました。 |
| 5 | 滋賀県 | 八田焼 | 滋賀県甲賀市 | 八田焼は、滋賀県甲賀市で作られている地域ブランドです。江戸時代の1655年(明暦元年)に、信楽から陶工を招いて作られ始めました。農家の副業として盛んになり、徳利・片口・神器・茶器などが焼かれてきました。 |
| 6 | 滋賀県 | 湖東焼 | 彦根藩本領(現・滋賀県彦根市域) | 湖東焼'(ことうやき)は、江戸時代後期に日本の彦根藩で始まった陶芸および、それによって生産される陶磁器である。湖東とは、彦根藩が所在した琵琶湖東岸を指す広域地名である。 青磁、赤絵や赤絵金彩、色絵などで絵付けした磁器が多く、大坂を経由して江戸など全国へ販売された。1829年(文政12年)に彦根藩本領(現・滋賀県彦根市域)で生産され始め、1842年(天保13年)に藩営化された。藩主井伊掃部頭家の許で発展したが、奨励・保護した井伊直弼が幕府大老在任中に暗殺されると職人が離散して一気に衰退し、明治時代に途絶した。その後、1986年(昭和61年)に復興事業が立ち上げられている。 |
